こんにちは、moruです。
経済とは簡単に言うなら、
お金を通じて人々が生活する仕組みのことです。
僕らは毎日生きて行くために食べるものや
着るモノなどを消費しながら生活していますよね。
そして、人々が消費するために必要なモノやサービスをつくるのが企業です。
多くの人は企業で働きながらお金を稼いで、
そのお金を消費に使っています。
そうやって経済は回っているわけです。
企業で働くほかにもお金を得られる手段はあって、
それが、企業に出資して株主(=オーナー)になることで、
差益や配当を得られるというものです。
3つの経済活動が自由に選択可能
この社会は以下の3つの経済活動を自由に選択して
生きて行くことが可能です。
以下、①②③は自由に選択可能です。
⓪消費は全員が該当
まず大前提として
モノやサービスを買う消費活動は全員が
毎日していることなのでこれは全員該当です。
①必要なモノやサービスをつくる企業で働く
「被雇用者になる」ということです。
例えば、その企業の社員やアルバイトなどで働き、
企業がモノやサービスをつくるのを手伝うことで、
毎月働いた分の決まったお給料がもらえます。
②必要なモノやサービスをつくる企業を創る
これを「起業」と言います。
人に必要とされるモノやサービスを開発し、
自らが社長(※株主)となって企業をつくる側に回ります。
※株式で資金調達などをしなければ、
社長がその企業の100%株主である場合がほとんどです。
③企業の株を買って差益や配当を得る
「株主になる」という表現だと
少し複雑に聞こえるかもしれませんが、
実際にはネット証券口座を作って株を買うだけです。
株を買うことによって、
その企業の株主(=オーナー)になれます。
何株買ったかは関係なく、
多かろうとほんの少しであろうと、
株を買った瞬間にその企業の株主になれます。
この方法をまだよく分かっていない人が
8割強いらっしゃるのが現状です。
教師が実際に株の教育をできないことが
日本教育の盲点だと思っています。
企業の他に国や地方自治体も経済活動を行っている
人々が生きて行くために必要なモノやサービスを
作っているのは企業だけではなく、
国や地方自治体もそうです。
国や地方自治体のことを「政府」と言います。
政府は国民や企業が納める税金を集めて、
必要なモノやサービスをつくっています。
例えば、社会に必要な道路や橋を作ったり、
子どもたちの生活に必要な公園を作ったり、
生活を守るために警察や消防、救急などを手掛けたりしています。
また、国公立の学校運営なども行います。
俗にいう公務員というお仕事は、
社長=政府みたいなイメージです。
政府の収入は「歳入」と呼ばれ、
逆に政府の支出は「歳出」と呼ばれます。
たまにニュースに出てきます。
参考まで財務省が毎年発表する歳入歳出を
以下に掲載しておきますね。
令和6年度一般会計予算 歳出・歳入の構成
これは財務省のHPに行けばいつでも見れます。
今回のまとめ
経済というのは、
- 人々の消費活動
に対して、
- 企業が人々に必要なモノやサービスをつくる
- 政府が人々に必要なモノやサービスをつくる
という需要と供給で常にお金を軸にして
回り続けているということです。
ご参考になれば幸いです。
それではまた!
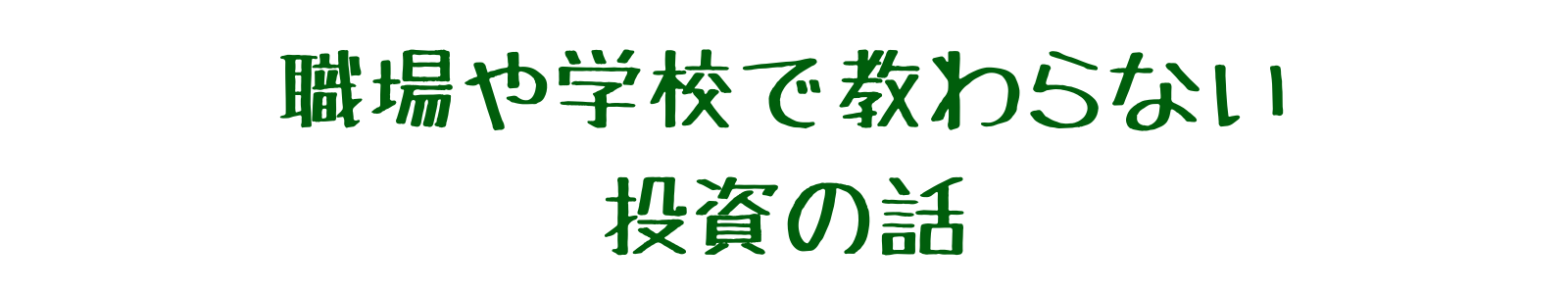
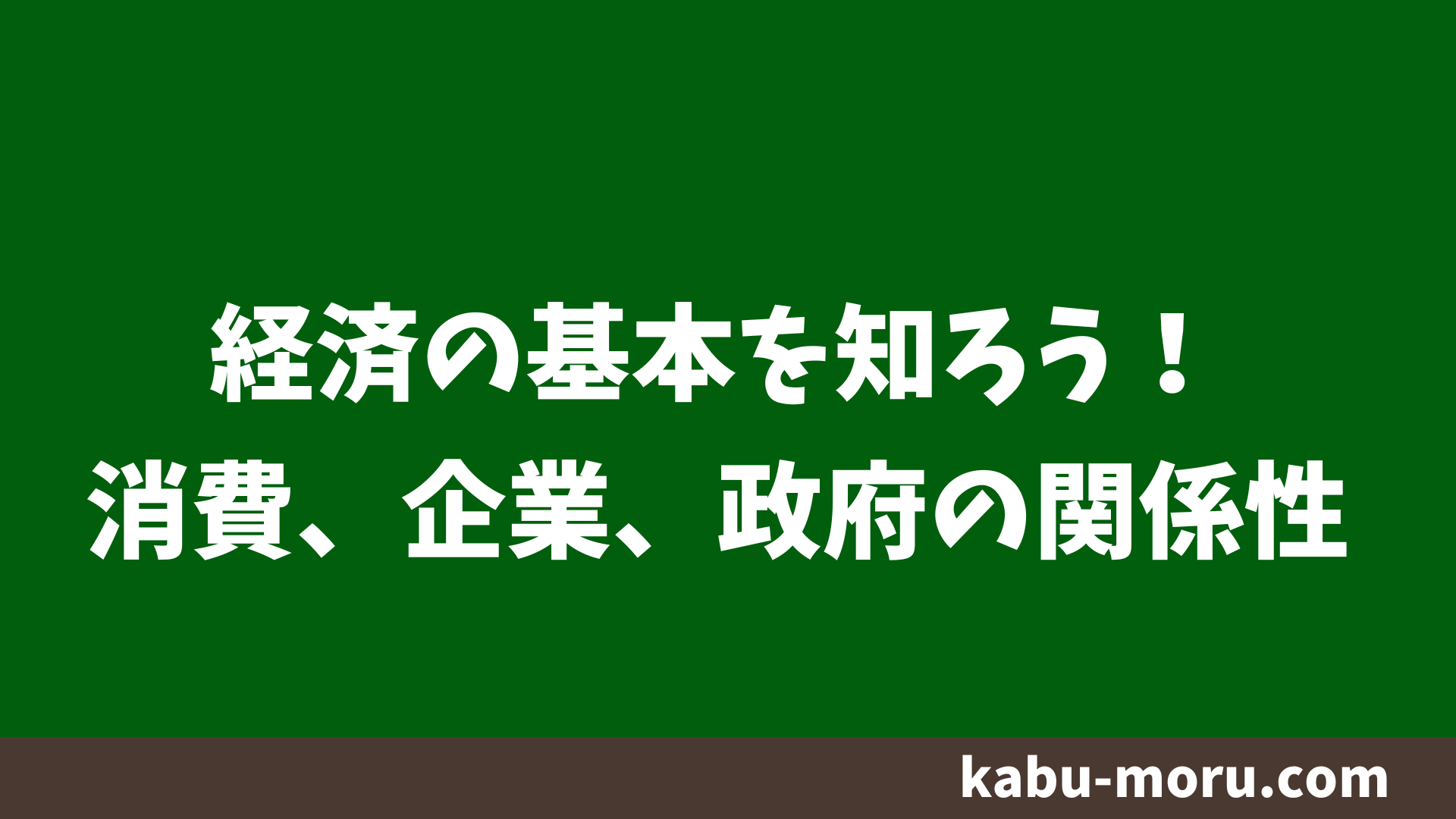
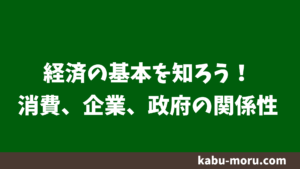
コメント